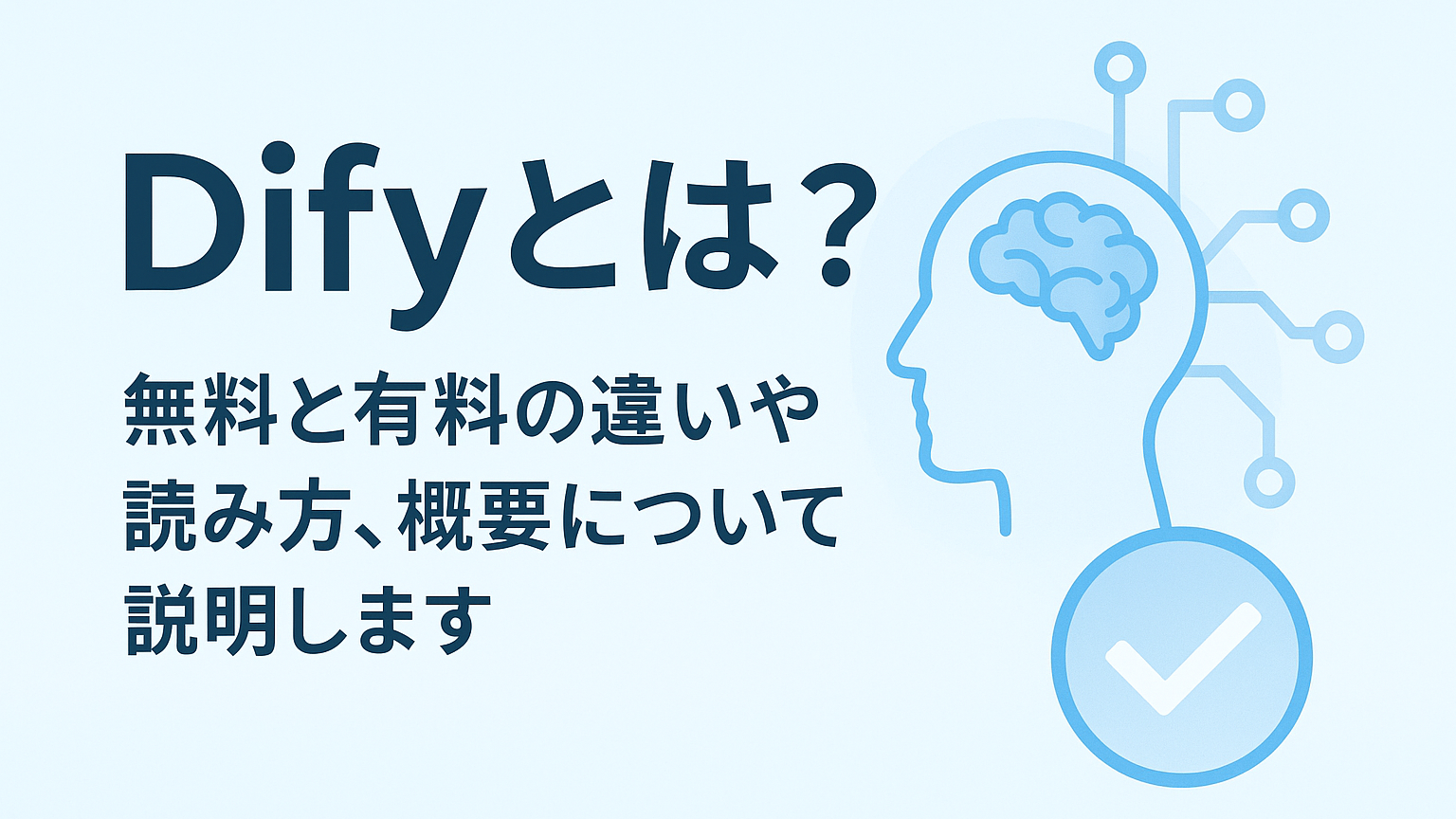
AIが世の中に浸透している最中、AIを活用したツール「Dify」の関心も年々高まってきています。
そこで今回は「Dify」について基本的な情報をまとめましたので、「Dify」に少しでも興味がある方はごらんください。
この記事で学べること
- Difyの基本的な概要について
- Difyの活用事例に関して
- Dify構築の仕方について
Dify(読み方:ディファイ)とは
Dify(読み方:ディフィ)とは、エージェント型ワークフロー、RAGパイプライン、各種インテグレーション、そして可観測性まで、必要なすべてを1つのプラットフォームで提供し、AIの力をあなたの手に委ねます。
一見難しそうな単語が並んでいますが、実践と並行して読み解いていくと、理解もしやすいかと思います。
特にDify上では直感的なUIでの操作が可能で、初心者にも優しい作りになっています。
Difyを扱うことであらゆるサービスとLLMを連結させることができます。
例えば、
- 社内検索bot:ドキュメントを横断的に検索し、自然言語で回答
- CXチャットボット:顧客対応を自動化し、会話データから改善点を発見
- SNS自動投稿:AIが下書きから投稿までをサポート
- ログ分析・アラート:異常検知や要約をAIが自動で行い、通知
等、多岐に渡ります。
一見すると「既存のサービスでもできそう」と思われるかもしれません。
しかし、ここに LLMの複合活用 を組み込むことは従来のサービスにとって難解でした。
Difyは、LLMの力を活かしてサービスを最適化・高度化することができます。
これこそが、Difyの真骨頂です。
Difyの無料・有料プランについて
続いてDifyのプランについて、紹介します。
Difyは無料でも利用することが可能です。
無料(サンドボックス)プランでも、アプリの作成やLLMとの連携は可能なので一度試す場合はこちらで問題ないです。
有料プランに関してはいくつか種類があるので、下記画像をもって解説します。(スマホでは見ずらいため、ズーム推奨ですが、後ほど見やすく表を記載します)

有料プランには「プロフェッショナル」と「チーム」の2つのプランがあります。
気になる価格ですが、プロフェッショナルが$59/月に対してチームが$159/月です。
日本円に換算すると安くはない金額ですが、アプリを多数使用したい方にとっては妥当な金額と言えるでしょう。
また、年次で購入すると2ヶ月分の料金がカットされるため、長期での利用を検討している方は年次で購入するとお得です。
また、学生や教育者は申請をすることでプロフェッショナルプランを無料で使用することができます。
詳細な比較は画像もしくは、下記表をご覧ください。※主要な部分をピックしています。
チームプランの上位としてエンタープライズがあるそうですが、サイト内では確認できませんでした。
利用したい方は問い合わせてみると、利用できるようになるかもしれません。
Difyで出来ることについて
続いてDifyでできることについて解説していきます。
- カスタマーサポート
- 営業支援
- 社内ヘルプデスク
- メディア運営
- 教育分野
他にも様々あります。正直やれことが多すぎて無限の可能性を秘めていると言っても過言ではありません。
例えば、自社のHPにカスタマーサポートのチャットボットを実装することも可能です。
Difyを取り入れていないチャットボットですと、あらかじめ用意された回答でしか返答できなく、
結局行き着く先は問い合わせ窓口になってしまうケースが多いです。
システム改善にも時間がかかるため、悩んでいる事業者も多いかと思います。
しかし、Difyを活用することができれば、あらかじめインポートした社内文書に基づいてRAGにより、回答をAIが生成してくれます。
これによりCXの質を大幅に改善することが可能です。
また、Difyはノーコード運用が可能ですので、チャットボットの修正やアップデートも簡単に行えます。